写真:岡 泰行
菅谷館の歴史と見どころ
菅谷館(すがややかた)は、鎌倉時代の有力武士である畠山重忠の館跡とされるが、その後の経緯などは解っていない。別名「菅谷城」ともいわれている。現在の城跡の遺構から戦国時代に大きく改修されたと考えられている。城の南側には都幾川が流れ、断崖を成している。東と西は自然地形の谷を利用した外堀があり、本郭、二ノ郭、三ノ郭、西の郭が放射状に列ぶ。昭和48年(1973)、菅谷館は国指定史跡に指定され、平成20年(2008)には「比企城館跡群菅谷館跡」と指定名称が改められた。現在、城跡の一角に埼玉県立「嵐山史跡の博物館」が設立、この地方の歴史の理解をより深めることができる。
菅谷館の関連史跡
ここ菅谷館跡に合わせ、比企城館跡群である、松山城、杉山城、小倉城などをどうぞ。
菅谷館のアクセス・所在地
所在地
住所:埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷 [MAP] 県別一覧[埼玉県]
電話:0493-62-5896(埼玉県立 嵐山史跡の博物館)
アクセス
鉄道利用
東武東上線「武蔵嵐山駅」下車、徒歩約15分。
マイカー利用
関越自動車道、東松山ICより国道254号線を西へ約11分(5.9km)。嵐山史跡の博物館の無料駐車場利用。







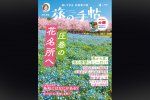






本丸、二の丸、三の丸、空掘り、土塁等が良く残っている。現在公園として整備されている。特に土塁は比高が4メータもあり圧巻である。国の史跡にも指定されている。埼玉で指定されている城は鉢形城とここ菅谷城のみ。
( 田村靖典)さんより
鎌倉武士の畠山重忠の館跡を、後北条時代に改修が加えられ現在にいたる。
( 田村靖典)さんより
埼玉県立歴史資料館の発行した資料パンフンに記載のあった「吾妻鏡」によると、鎌倉に異変ありとの急報に接した重忠は、わずか134騎の手勢を率い「小衾郡菅屋館」を出発しとある。この菅谷館が、今日の菅谷館跡と見なされますが、現存する遺構は全て戦国期のもので、実際に重忠時代にさかのぼる遺構は見つかっていません。このように書かれていて、遺構は戦国期のものであるようですが、誰が居城したかは説明されていません。ただ二の曲輪は中央付近から枡形の「馬だし」があり、戦国時代の終わりの頃とみられています。管領上杉氏が内部争いした頃に、この地域はほとんど城郭はつくられていたようで、菅谷館もこの時期に手を加えられ、後北条が支配した頃に増改築されたのではないでしょうか。
( 横尾)さんより